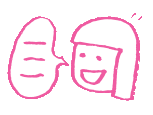d-lab2024 2日目のプログラム
- プログラムC(分科会)は事前予約制です。
- 分科会の定員は、各回30名程度です。2日目は会場のみ(ハイブリッド開催はなし)の実施です。
- プログラムは「中学生以上」からお申し込みいただけます。
10時~15時30分 課題別分科会
C.課題別分科会
第1分科会
【残席僅か】なぜ難民を受け入れるのか
- ゲスト:橋本直子(国際基督教大学)、長谷川留理華(Human Welfare Association、無国籍ネットワーク)
- 進行:木下理仁(東海大学国際学部非常勤講師、『難民の?がわかる本』著者)
- 共催:東海大学国際学部

橋本直子(国際基督教大学)
国際基督教大学准教授。政治・国際関係学デパートメントで国際法(主に難民法や国際刑事法、国際機構論)を担当。大学院卒業後15年近く、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国際移住機関(IOM)、外務省、法務省等で、人の移動、人権問題、難民保護、移民政策等について実務家として勤務。著書に『なぜ難民を受け入れるのか-人道と国益の交差点』(岩波新書)など。

長谷川留理華(HUMAN WELFARE ASSOCIATION、無国籍ネットワーク)
ミャンマーのラカイン州(アラカン)で生まれ、1992年からは家族とともに首都ヤンゴンで、ロヒンギャ民族であることを隠して生活していたが、たび重なる迫害や差別から、2001年に日本に逃れる。2013年、日本国籍を取得。HUMAN WELFARE ASSOCIATION 代表、無国籍ネットワーク共同代表。ロヒンギャ語の翻訳、講演活動、料理教室なども行っている。
世界では1億2千万人もの人々が、紛争や迫害などによって家を追われていますが、日本の受け入れ人数はごくわずかです。
・なぜ「難民」になり、なぜ日本に来るのか
・難民は日本でどのように生活しているのか
・なぜ難民を受け入れなくてはならないのか
・なぜ日本は難民の受け入れに消極的なのか
・入管法改正をめぐる議論とは何だったのか
・入管法が変わって、これからどうなるのか
そうしたことがらについて、「難民」として日本に逃れてきた当事者である長谷川留理華さんや、国連機関や法務省などで難民に関わる実務に携わり、現在は研究者の立場から政策提言を行っている橋本直子さんにお話を聞いて、とくに「教育」の場でこの問題をどのように扱っていくべきか、参加者全員で考えます。
※可能な方は『難民の?がわかる本』(木下理仁著、太郎次郎社エディタス)と『なぜ難民を受け入れるのか-人道と国益の交差点』(橋本直子著、岩波新書、6月20日発行予定)を読んでから参加されることをおすすめします。
※本プログラムには10名程度、東海大学の学生がフィールドワークとしてプログラムに参加いたします
第2分科会
公正で平等な社会づくりのために:『教育をジェンダー視点で見直すヒント集』を使って
- ゲスト:鈴木啓美(ピープルツリー)、谷田なつ美(小学校教員)
- 進行:近藤牧子(DEAR)、岩岡由季子(会社員)、開発教育とジェンダー研究会

鈴木啓美(ピープルツリー)
広報・啓発担当。自身も長年ピープルツリーの愛用者だったことから、多くの方にフェアトレードを身近に感じ、生活の中に楽しく取り入れてもらえるよう、メディア対応、記事制作、イベントやトークセミナー「フェアトレードの学校」の企画&講師などを務める。

谷田なつ美(小学校教員)
小学校教員。JICA教師海外研修にて、国際理解教育/開発教育を学ぶ中、DEARに出会う。翌年、JICA日系社会青年ボランティアとしてブラジルで活動する。帰国後も国際理解教育/開発教育を実践している。また、校種を越え、様々な場所でワークショップや出前講座なども実施している。
「公平で平等な社会」ってどんな社会でしょうか。そんな社会づくりのために私たちは、何ができるのでしょうか。一人の市民・社会の構成員として何かをしたい。でも何をすれば良いのかわからないこともあります。私たちは、すべての人が自分自身のジェンダーバイアスに気づくことが「公平で平等な社会」をつくるための重要な一歩だと考えています。バイアス(偏り、偏見、先入観)は、誰にでもあることなので、そのこと自体非難されることではありません。でも、バイアスがあることに気づき、日々の自分のふるまいに自覚的になることで、日頃提供している授業や研修プログラム、あるいは人とのコミュニケーションが変わってくるはずです。この分科会では、今年発刊した『教育をジェンダーの視点で見直すヒント集』の使い方を丁寧に紐解き、活用いただけるようになることを目指します。また、「公平で平等な社会」ではない現状の分析方法も解説します。
※『教育をジェンダーの視点で見直すヒント集』をお持ちください。当日購入も可能です。
第3分科会
ムクウェゲ医師、平和への闘い~紛争鉱物問題のいま
- ゲスト:華井和代(NPO法人RITA-Congo共同代表)、吉崎亜由美(桐朋女子中学校・高等学校)
- 進行:八木亜紀子(DEAR)

華井和代(NPO法人RITA-Congo共同代表)
コンゴの紛争鉱物問題と日本の消費者市民社会のつながりを研究。2019年にNPO法人RITA-Congoを設立して共同代表に就任した。また、元高校教師の経験を生かして平和教育教材を開発・実践している。『スマホから考える 世界・わたし・SDGs』に制作参加。主著は『資源問題の正義―コンゴの紛争資源問題と消費者の責任』(東信堂、2016年)。

吉崎亜由美(桐朋女子中学校・高等学校)
桐朋女子中・高等学校(社会科)教諭。映画「ムクウェゲ 女性にとって世界最悪の場所」(立山芽衣子監督)の中で、高校地理で行った授業『スマホから考える 世界・わたし・SDGs』の様子が紹介されている。主な近著に『SDGs時代の地理教育「地理総合」への開発教育からの提案』(共著、学文社、2024)がある。
みなさんは、紛争鉱物ということばを聞いたことがありますか。紛争鉱物とは、採掘や取引から得られる利益が紛争の資金源となっている鉱物のことです。コンゴ民主共和国では、レアメタルや錫などの多くの種類の鉱物が紛争に利用されています。また、武装勢力によって、性暴力が組織的に行われています。この紛争の原因は、わたしたちの生活と無関係ではありません。わたしたちが身近に利用しているスマホや電子機器とつながっているのです。しかし、コンゴ民主共和国の現状やムクウェゲ医師の闘いについて、日本ではあまり知られていません。これは、見えにくく、認識されにくいけれども誰もが加担してしまっている「構造的暴力」の状態にあるといえます。
そこで、学校教育や社会教育の題材としてムクウェゲ医師や紛争鉱物について取り上げることを検討してほしいと思い、分科会を企画しました。分科会では、DEARの教材『スマホから考える世界・わたし・SDGs』を体験します。そして、「わたしたちにできること」をワークショップ形式で考え、参加者のみなさんと「構造的暴力」と「平和」について議論します。
<リソース>
・教材『スマホから考える 世界・わたし・SDGs』(DEAR)
・岩波ジュニア新書『ムクウェゲ医師、平和への闘い』6月20日刊行 (華井・立山・八木共著)
・学文社『SDGs時代の地理教育』4月刊行(吉崎共著)
第4分科会
気候変動を学ぼう~変化の担い手になるために
- ゲスト:三谷優衣子(クライメート・リアリティ・プロジェクト・ジャパン)、Nguyen Kieu An(グエン・キエウ・アン)(CRPインターン/ベトナム)
- 進行:中村絵乃(DEAR)

三谷優衣子(クライメート・リアリティ・プロジェクト・ジャパン)
気候変動対策に取り組む国際NGO、クライメート・リアリティ・プロジェクト・ジャパン支部マネージャー。書籍執筆を含む様々な環境教育に取り組む。特に関心のある領域は気候正義や気候変動に影響を受ける人権問題(労働者の人権やジェンダー、難民問題など)。神奈川県出身、英国ノッティンガム・トレント大学卒。

Nguyen Kieu An(グエン・キエウ・アン)(CRPインターン/ベトナム)
ベトナム・ハノイ出身。岡山大学の4年生、政治学専攻。2023年2月からクライメート・リアリティ・プロジェクト・ジャパンのインターン生。脆弱者向けとグローバル・サウスにおける気候正義に関する活動に取り組む。特に社会から疎外されたグループのニーズを優先する公正かつ公平な政策立案プロセスに関心を持つ。
気候変動は、全世界において経済や社会、人々の暮らしやシステム自体に多大な影響を与えています。その影響は貧困層や最も脆弱な人々の生命を脅かしています。現状を前にして、私たちには何ができるでしょうか。
本分科会では、アクティビティを交えて、気候変動の問題や影響を理解したうえで、世界で気候変動対策に取り組むネットワーク団体、CRPジャパンからゲストをお招きし、気候変動の仕組みや実際に行われている様々な取り組みを学びます。個人でできる生活の中の選択を中心とした対策を越えて、より大きな変化の担い手になるために、一緒に考えましょう。
第5分科会
【申込締め切りました】「社会を変える学び」とは?~SDGs学習を考える
- ゲスト:荻野亮吾(日本女子大学)、加藤英嗣(小学校教員)、中村拓海(小学校教員)
- 進行:DEAR内SDGs研究会 田中治彦(DEAR監事) 、松倉紗野香(DEAR副代表理事)、本山明(法政大学)

荻野亮吾(日本女子大学)
日本女子大学人間社会学部・准教授。専門は社会教育学、成人教育学。社会教育を通じた地域社会のつくり方に関心を持つ。主な著書・訳書に、『地域社会のつくり方』(勁草書房、単著、2022年)、『地域教育経営論』(大学教育出版、共編著、2022年)、『コミュニティを研究する』(新曜社、監訳、2023年)ほか。

加藤英嗣 (小学校教員)
DEAR評議員、DEAR授業づくりサークルメンバー。東京都公立小学校に勤務。ナイロビ日本人学校への海外派遣を経験。開発教育の「知り・考え・行動する」という学びのプロセスを活用しながら、地域のフィールドワークを通して問題解決を図る総合的な学習の実践に多数取り組む。

中村拓海(小学校教員)
都内公立小学校勤務。7年前から先生たちの学びの場である「ティーチャーズ・イニシアティブ」に参加し、探究学習と出会う。SDGsや地域課題をテーマに毎年、探究学習を行っている。休日はボランティアで少年サッカーのコーチを行う。
街を歩いていてもテレビをみていても、そして教科書を開いても…SDGsのロゴが溢れるようになりました。SDGsという言葉もカラフルなロゴのアイコンも身近にはなっていますが、果たしてわたしたちが暮らしている社会はSDGsの達成に向けて「変容」を遂げているでしょうか。
政策や教科書の内容をSDGsと関連づけることが果たして「SDGs学習」でしょうか。SDGsについて知るだけでは、社会は変容しません。SDGsが掲載されているアジェンダのタイトルは「Transforming Our World」です。わたしたちは何をどのように「変容」していかなくてはいけないのでしょうか。社会を変容するための学びについて、社会教育、学校教育など多様な場を舞台に議論してみませんか。
15時45分~ ふりかえり会、閉会式
2日間学びや気づきを参加者同士で共有します。
ネットワークづくりにもお役立てください。
1日目
- 1日目(3日)のプログラムはこちら
参加申込
事前のお申込みをお願いします。
お申し込み後、参加費のお支払いいただくと正式なお申込受付となります。
※ 各プログラムは定員に達し次第締め切ります。
手続き詳細・お申込みはこちらのページからどうぞ